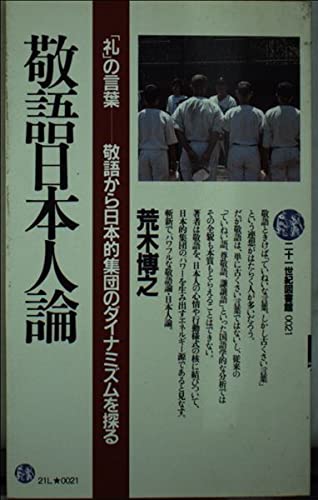| 敬語ときけば,ていねいな言葉,しかし古くさい「言葉」という連想が働く人が多いだろう.だが敬語は,単に古くさい言葉ではないし,従来の「ていねい語」「尊敬語,謙譲語」といった国語学的な分析ではその全貌も本質もとらえることはできない――. |
敬語は単なる尊敬語,丁寧語,謙譲語にとどまらない.敬語には日本人の心情が深く関わっている.その敬語を喪失するということは,日本人にとって重大な損失になる.そのことにわれわれは気づいていないのだ.その問題意識で日本人にとっての敬語の論点を探り当てた本である.文化と社会と言語――それらを結び付けるのは,民俗学的観点からのアプローチとなる.いわゆる"敬語不要論"の論拠は,日本の敬語は封建的な上下関係がはぐくんできた言語体系であるから,民主主義とは対立する言語形態,というものである.この趣旨は30年以上,ほとんど変化せず乱発されてきた.敬語は人と人の上下関係を前提とする.しかし,上下関係のない民主的社会などありえるだろうか.
2000年の国語審議会答申「現代社会における敬意表現」の中で,この「上下」という言葉は意図的に避けられた.答申では「コミュニケーションにおいて,相互尊重の精神に基づき,相手や場面に配慮して使い分けている言葉遣いを意味する」「話し手が相手の人格や立場を尊重し,敬語や敬語以外の様々な表現からその時々にふさわしいものを自己表現として選択するものである」と定義した.敬語の「上下」というのは,身分の固定だけを表すものではない.状況に応じて,上下関係はめまぐるしく入替わる.教師も市井の人であれば,習い事の初心者なら「門前の小僧」であり,主客は入替わる.そういった社会関係の位置の変化は,まっとうな社会なら当然ありうることである.敬語は単に人間関係の上下を規定する役割だけを持っていない.格付けとしての語法だけをとらえる解釈が誤りだという本書の主張は,敬語を言語論としてだけとらえることではいけないと,日本文化との位置関係に分け入っていく.
言語というものが文化と密接につながっている,というのは,ヴィルヘルム・フォン・フンボルト(Wilhelm von Humboldt)以来の学説である.フンボルトは,言語と精神との緊密な関係を重視して,言語は精神によって形成され,その精神活動の産物が言語に表出される繰り返しの連続だと動的言語観を主張した.その言語の中で,敬語が孤立した存在ではないと考えたのが,アメリカの言語学者J.V.ネウストプニー(Neustupny, Jiri V)であった.敬語は「非言語的なエチケット」「ことばづかいのエチケット」とならんで,「敬意セクター」をなしている敬意表現の1つと彼は考えた.この敬意セクターという考え方に,本書は賛同を唱える.さらに,そこに独自の概念を加えている.それが「他律」という概念であった.
《自発》は《他律》と本質的な交換関係にはない.《受身》《没主体》《自己滅却》《集団論理》は,構成要素として《他律》よりも上位関係にはないとここでは仮定する.鍵概念としての他律は,最も普遍的でその裾野も広い.そして記号の構成要素が複雑になればなるほど反比例的に裾野は狭くなってゆくが,その鍵概念と重なる構成要素を持った文化的事項の説明はより具体的に,絵画的になっていくのである.相手が尊敬できると判断する,あるいは尊敬すべきと判断する.これがすなわち,敬語行動の本質である.本書の表現にすなおに従うなら,「自己を空しくする」ということになる.この「空しく」というのは,けっして「空虚」を意味していない.「主体が不在」ということを意味している.「あの日のことが思い出されてならない」の「~されて」というのは,意識せずとも自然と脳裏によみがえってくる情景のことを尊ぶことを示す表現なのだ.これが,自己を空しくする,ということなのである.
結局のところ,本書は敬語を律法の行使の手段としてとらえ,その回復と機能を願って敬語を取り上げたということになる.目上の人を敬わなければならない,という表層的な敬語論を超えて,敬語行動の廃棄を懸念し,その復権こそが文化的荒廃を遠ざける術だと説明する.日本的心情にコミットする敬語活動は,この国の価値体系のあり方と生活規範にその位置づけが確立されるべきだということだ.その一方で,著者は敬語行動の行使は律法者側の愛情にかかってくるであろうということ,また本書を自戒の書としめくくる.「敬語的人間」というものがいるとすれば,自分はまことに程遠い人間であるということを実感してしまったからである.
++++++++++++++++++++++++++++++
原題: 敬語日本人論
著者: 荒木博之
ISBN: 4569211399
© 1983 PHP研究所